こんにちは。今回は、国立障害者リハビリテーションセンター(通称:国リハ)に入所していた約1年間の体験談をお話しします。
私が入所したのは、ちょうどコロナ禍の真っただ中。日々変わる状況のなかで、どのようにリハビリに向き合い、何を感じたのか。これから国リハに入所する方やそのご家族の参考になればうれしいです。
入所当初の不安と痛み
私が入所したのは、頸髄損傷などの人が「できること」を増やすための訓練を行う「機能訓練棟」でした。
最初に感じたのは、「1日中、車いすで過ごす生活に自分が耐えられるのか」という大きな不安です。国リハでは1日12〜14時間ほど車いすに座って過ごします。
私は鈍いながらも下半身に感覚が残っていて、特に右のおしり(右臀部)がズキズキと痛くなることが多く、本当にきつかったです。スタッフの方に相談し、クッションや姿勢の調整をしながら、少しずつ座る時間を延ばしていきました。
コロナによる外出制限と隔離
入所して1ヶ月ほどで、コロナの影響によって外出に制限がつきました。病棟内で陽性者が出たのかは伝えられませんでしたが、突然の“封鎖状態”に。
その後、私自身も熱が出て、数日間は個室で隔離生活となりました。誰とも会えず、訓練も止まり、不安と孤独を感じる時間でしたが、看護師さんやスタッフの声かけに支えられました。
パソコン操作の再習得
リハビリには、日常生活を取り戻す訓練も含まれます。私は指がうまく使えない状態だったので、トラックボールや自助具を使って、パソコン操作を一から練習しました。
入力方法や設定の工夫を知ることで、「もう自分には無理かも」と思っていたことが、実はまだできる!と気づけたのは大きな自信になりました。
リハビリスポーツの力
国リハでは、身体の動きだけでなく、楽しみながら訓練ができる「リハビリスポーツ」にも力を入れています。
最初は、車いすの基本的な操作や応用動作を、実際に体を動かしながら練習します。たとえば、バランスを取る練習や、後ろ向きに進む動き、急な方向転換などです。
さらに、バランスボールを使ってバレーやサッカーのような動きも取り入れられました。気づけば夢中になってムキになっていた自分がいました。
自動車訓練で広がる行動範囲
国リハには、障害の状態に合わせた改造車を使った「自動車訓練」もあります。
最初は、教習所のような専用コースで実車を使って練習します。私のように左足でアクセルとブレーキを操作するタイプの改造車にも対応していて、自分に合った運転方法で安全に練習できました。
そして、免許の更新ができたら、実際の道路での訓練も行います。信号や合流、交通ルールを確認しながら、現実に近い環境での練習ができました。
面会の時間が救いだった
コロナ禍でも、国リハでは事前予約制で面会が可能でした。専用の面会室で、短い時間ではありましたが、家族と直接会って話せる時間は何よりの救いでした。
「会いたい人がいる」「見守ってくれる人がいる」ということが、大きな支えになりました。
自助具でひろがる「できること」
退所後を見すえて、私に合った自助具の作成や生活の工夫も教えてもらいました。
- 坐薬挿入器の個別作成
- スマートロック(Qrio Lock)の活用方法
- 鍵を持ちやすくするための3Dプリンタによるグリップ加工

こうした工夫ひとつひとつが、「自分の力で暮らしていく準備」になりました。
国リハで得たもの
どれも、今の私にとって大切な財産です。
まとめ
コロナ禍という特殊な状況の中、国リハでの入所生活は楽なものではありませんでした。
でも、その中で得られた経験と気づきは、これからの生活を前向きに歩む力になっています。
退所後の生活の工夫や、使っている自助具、外出に関することなどは、別の機会に紹介したいと思います。

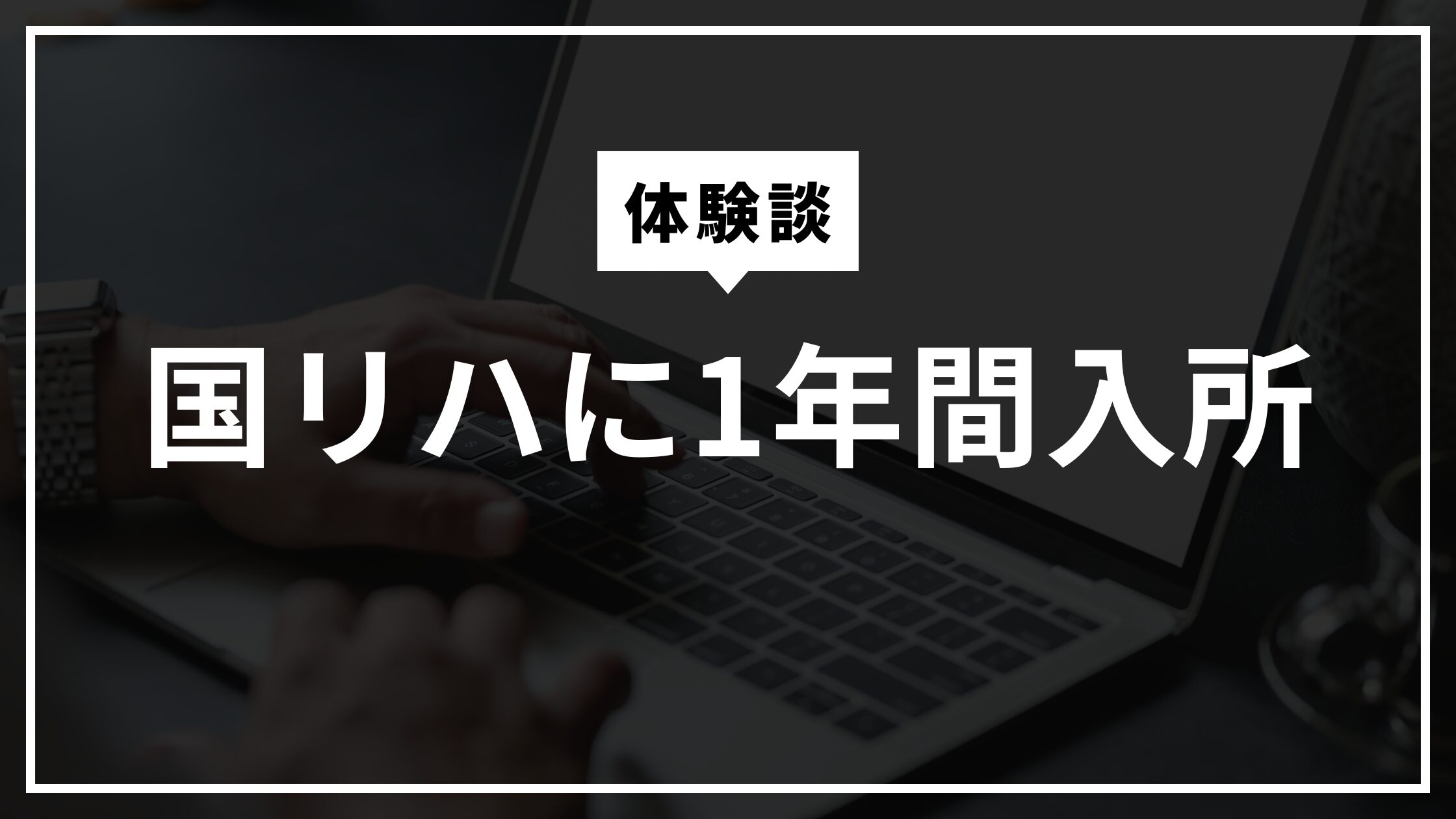
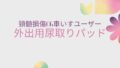

コメント