頸髄損傷C6レベルで車いす生活をしている私が、生活の困りごとをどうやって調べて解決しているかをご紹介します。
✅この記事はこんな人におすすめです
- 頸髄損傷などで車いす生活を始めたばかりの方
- 障害のある方の介助・支援をしている家族やヘルパー
- 入浴・排泄・着替え・外出などの生活工夫を探している方
- 検索やSNS、本などの活用方法を知りたい方
- 同じような立場の人の経験談を知りたい方
✅この記事の結論(先に知っておくと便利です)
- 検索キーワードを工夫するだけで、役立つ情報が見つかる
- SNSやYouTubeにはリアルな声が多く、実際の動きがわかる
- リハビリ病院や仲間の知恵は、何より実用的
- 本から得られるのは「気づき」や「生き方のヒント」
- 情報は、待たずに探しにいくことで出会える
きっかけは「わからなさ」から
私は事故によって頸髄損傷となり、C6レベルで車いす生活になりました。
最初は何もわからず、あらゆる生活動作に不安がありました。
- 靴がうまく履けない
- トイレはどうしたらいいのか
- 自宅でお風呂に入る方法は?
- 暑い日の外出はどうすれば快適になるのか
入院中に教えてもらったことも、あとから思い出せず苦労した経験もあります。
ネット検索は「言葉の選び方」がカギ
まずやるのはネット検索。でも「どう調べるか」がとても大事です。
「お風呂」で調べるよりも、「C6 入浴方法」「車いす 移乗ボード」のように、少し専門的なワードを入れると、情報の精度が変わってきます。
わからない言葉はすぐにメモ。調べる→学ぶ→また調べる…の繰り返しが、自分に合った情報に近づくコツです。
YouTubeやブログで「実際の動き」がわかる
文字だけでは伝わりにくいのが、動作や介助の流れ。
そんなときはYouTubeが大きな味方です。
- シャワー
- ベッドから車いすへの移乗方法
- トイレ・入浴動作の工夫
同じC6レベルの方が出ている動画なら、自分にも当てはめやすいです。
ブログでは、グッズのレビューや使い方、失敗談も参考になります。
SNSは「調べる」より「つながる」
X(旧Twitter)やInstagram、スレッズなどのSNSも活用しています。
「#頸髄損傷」「#車いすユーザー」などのハッシュタグをたどることで、他の人の投稿を探したり、DMで直接聞くこともあります。
検索では見つからなかったものが、人との会話の中で見つかることもあります。
病院や仲間からのリアルな情報は宝
私は国立障害者リハビリテーションセンターに入所していたときに、他の入所者さんやスタッフからたくさんのことを教わりました。
- 入浴時の移乗方法
- 安全なシャワーキャリーの選び方
- ベッド上での姿勢保持方法
実際に見て、試せる環境で得た情報は、ネット以上に信頼できます。
書籍から得る「実用」も「心の支え」もある
調べごとをするとき、本から得る知識も私にとっては大切です。
『ひまわり』(新川帆立)
この小説は、障害を持つ登場人物の視点が描かれています。
悩みや葛藤、そしてそれを乗り越える姿がリアルで、自分の気持ちとも重なり、「こう考えてもいいんだ」と心が軽くなりました。
『iPadがあなたの生活をより良くする』(安保雅博・高尾洋之)
こちらは、iPadを使って生活を便利にする方法を解説した実用書。
身体に障害がある人向けの工夫やアプリ活用法が多数紹介されていて、実際に私がiPadを使うきっかけになった一冊です。
「こうすればできる」が詰まった本でした。
調べても見つからないときは、発信してみる
どうしても情報が出てこないときは、自分で発信するのも手です。
ブログやSNSで「こういうことで困っています」と投稿すると、誰かが教えてくれることもあります。
情報収集は一方通行ではなく、「人とやりとりすること」も大きなヒントになります。
おわりに:生活のヒントは、あちこちにある
私のような頸髄損傷C6の車いすユーザーでも、工夫次第で自分らしく生活を続けていけると感じています。
情報を探すときのポイントは――
- 言葉を工夫して検索
- SNSやYouTubeでリアルな声に触れる
- 本から知識と勇気をもらう
- 仲間の知恵を借りる
- 発信することで情報が集まる
小さな行動が、大きな安心につながります。
あなたにも、あなたらしい工夫がきっと見つかります。



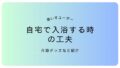
コメント