対象読者と結論
- 車いすや歩行が不安定な方、そのご家族
- 障害当事者の声に関心のある方
- バリアフリーを考える行政・スタッフの方
結論(先に伝えます)
- スロープがあっても「使いやすい動線」がなければ意味がない
- 配慮のつもりが、かえって負担になることもある
- 「行きやすく、帰りやすい」投票所を目指してほしい
1. スロープはある。でも「配慮されてる」とは言えない
選挙の日、投票所の入り口にスロープがあるのは当たり前になってきました。これはとてもありがたいことです。けれども、実際に入ってみると、**「本当に車いすユーザーのことを考えて作られたのかな?」**と感じる場面がいくつもあります。
たとえば、スロープをのぼって中に入ると、投票台は部屋の一番奥。しかも、通路が狭くて人とすれ違いづらい。スタッフの人は親切に声をかけてくれますが、「なぜここまで行かなきゃいけないんだろう」とモヤモヤ。
2. 出口が段差!? 結局「入り口から戻る」しかない
もっと困ったのが、「出口に段差がある」ケースです。
「入口にスロープがあるから安心」と思って進んでいったのに、投票を終えて出口へ向かうと、そこに階段。つまり、入り口から入って、また同じルートを引き返さなきゃいけないのです。
投票は一人ひとりが大切にするべき行動なのに、**「迷惑かけてるかも」「邪魔かも」**と思ってしまうこの動線設計には、正直ストレスを感じました。
3. 「配慮」はあるけど、当事者の目線とはズレている
バリアフリーは見た目だけではわかりません。
たとえば、車いす用の低い机が設置されていても、それが投票台からかなり離れた場所に置かれていたり、仕切りがなかったりすると、**「見られているかも」「落ち着かない」**と感じてしまいます。
スタッフの方が「どうぞこちらへ」と案内してくれるのはうれしいけど、「なるべく目立たないようにしたい」と思っている人もいる。「優しさ」が空回りしないよう、当事者の声をもっと取り入れてほしいと思います。
4. 解決するには?3つのポイント
では、どんな投票所なら「本当にバリアフリー」だと言えるのでしょうか?実体験から考えたポイントは以下の3つです。
① スロープだけでなく、出口までの「動線」を整える
- 入り口と出口、両方にスロープがある
- 投票までの通路が広く、すれ違いやすい
② 車いす用の投票スペースは、普通の場所と同じ並びに
- 特別扱いではなく「自然に」使える
- プライバシーもきちんと守れる工夫を
③ 事前に「情報を公開」する
- バリアフリー対応の有無をWebで見られるように
- 下見できるような柔軟な対応も
5. まとめ:誰もが「自分の一票」を安心して投じられるように
選挙はすべての人にとって大切な権利です。
けれども、バリアフリーの視点が抜けていると、投票所に行くことすら大きなハードルになります。スロープを置くだけでは足りません。「使いやすさ」や「心理的な安心感」まで配慮してこそ、本当の意味でのバリアフリーです。
これからの社会が、もっと誰にとってもやさしい場所になるように。小さな気づきの積み重ねが、大きな改善につながります。投票所もそのひとつ。もし関係者の方がこれを読んでいたら、どうか**「実際に使っている人の声」**に耳を傾けてほしいと願っています。

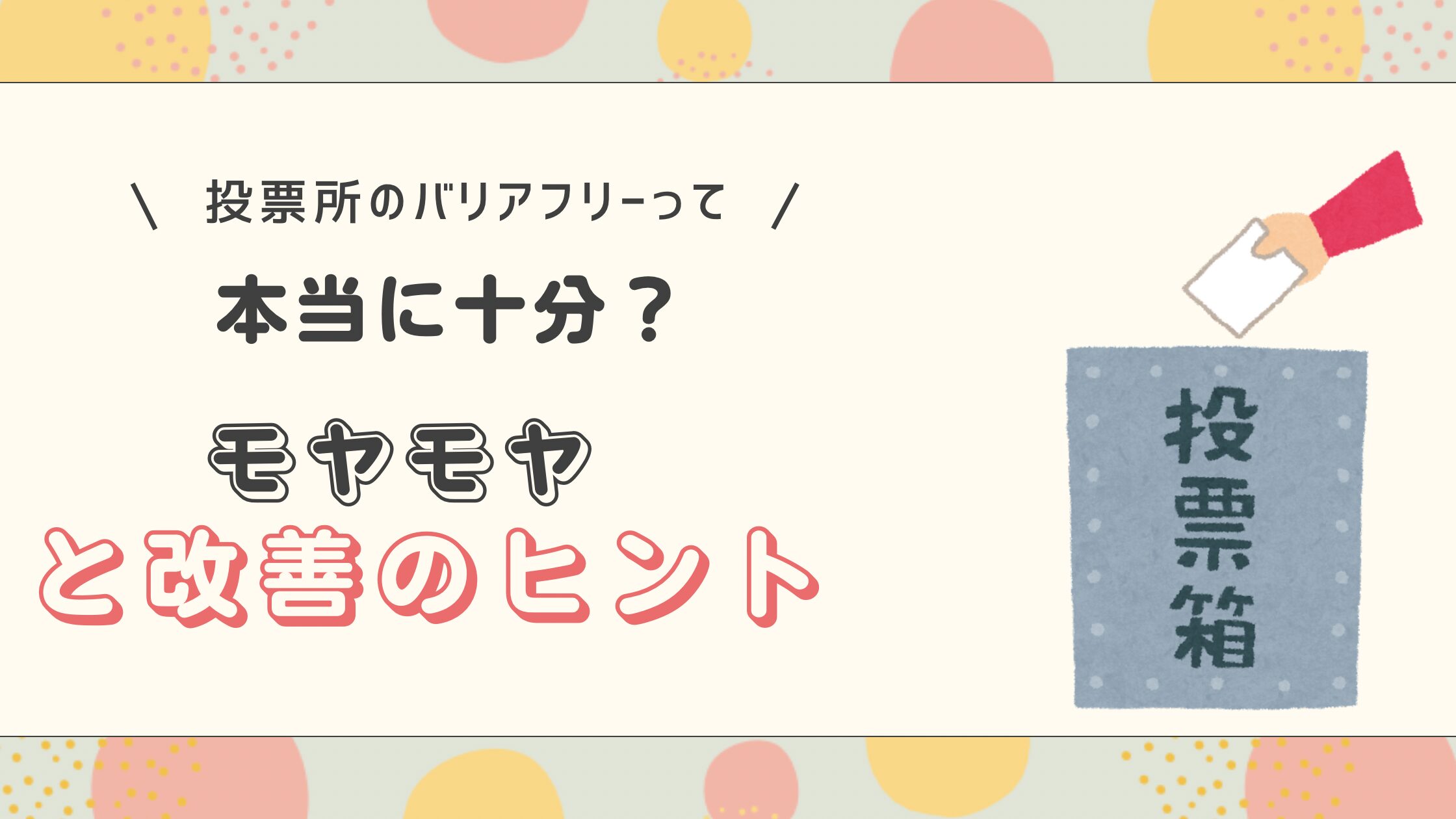
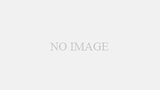

コメント