対象者と結論
✅対象者
- 車いすを使って生活している人
- 電車やバスなどの公共交通機関で外出する予定がある人
- 身体障害者手帳などを持っている人
✅結論
- 障害者用Suica・PASMOがあれば、運賃が割引になって経済的
- きっぷを買わずに、自動改札にタッチするだけでOK
- とくに「改札を出るとき」の手間がなくなり、外出がぐんと楽になる
電車移動に便利な「障害者用Suica・PASMO」とは?
車いすを使って電車に乗るとき、券売機の操作がしづらかったり、窓口に並ぶのが大変だったりすることはありませんか?
そんなときにおすすめなのが、「障害者用Suica」や「障害者用PASMO」です。
これは、ふつうのICカード(SuicaやPASMO)に、障害者割引の機能をつけた特別なカードです。
身体障害者手帳などを持っている人が対象で、事前に申し込めば誰でも使えます。
どんな割引があるの?
交通事業者によって違いはありますが、多くの電車やバスで運賃が半額程度になります。
たとえばJR東日本の場合、片道101km以内の乗車であれば、本人と同伴者1人までが割引の対象になります。
地下鉄やバスなど、首都圏の私鉄でも、同じように割引が受けられるところがたくさんあります。
しかも、割引が自動で適用されるので、いちいち申し出る必要がありません。
きっぷを買う手間がなくなり、タッチだけで改札を通れるのはとても快適です。
どこで申し込める?
障害者用のSuicaやPASMOは、次の場所で申し込めます。
- JRの場合:「みどりの窓口」
- 私鉄や地下鉄の場合:定期券売り場(有人カウンター)
申込時に必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 身体障害者手帳や療育手帳など
- 証明写真(必要な事業者もあります)
駅によっては対応していないところもあるので、事前にネットや電話で確認してから行くのがおすすめです。
実際に使ってみて感じたメリット
私は首をケガして車いす生活になりましたが、障害者用のPASMOを使い始めてから、本当に外出が楽になりました。
特に便利だと感じるのは、**駅の「改札を出るとき」**です。
以前は、割引を受けるために、改札横の「みどりの窓口」や、駅員さんがいる通路に行って、いちいち精算していました。
でもこのカードがあれば、自動改札にそのままタッチするだけで、ちゃんと割引が反映された運賃で通れるんです。
スーツケースを持った人が行列している有人改札を避けて、自分のペースでスイスイと移動できるのは、精神的にも大きな助けになります。
「今日はあまり人に頼りたくないな…」という日も、このカードがあれば安心です。
注意点もあるのでチェックしよう
便利な障害者用Suica・PASMOですが、以下のような注意点もあります。
- 利用できる路線に制限がある(すべての交通機関で使えるわけではない)
- JRでは101kmを超える長距離には適用されない場合がある
- 同伴者の割引は、必ず一緒に入場・出場しないと無効になる
- 障害者割引の登録は「年に1回」更新が必要。手帳の確認のため、窓口での手続きが必要です
- スマホ版やApple WatchのモバイルSuicaには、障害者割引機能はつけられない(必ず物理カードを使うこと)
うっかり更新を忘れると、通常運賃が引かれてしまうので、毎年の更新はカレンダーにメモしておくのがおすすめです。
まとめ:外出の自由をサポートする、強い味方
障害者用のSuica・PASMOは、車いすユーザーにとって**「移動の自由」を支える大きな力**になります。
割引が受けられておトクなだけでなく、改札を出るときに人の手を借りなくていい安心感は、想像以上です。
最初は少し手続きが面倒かもしれませんが、一度作ってしまえば毎日の移動がぐっと快適になります。
まだ持っていない方は、ぜひこの機会に検討してみてください。

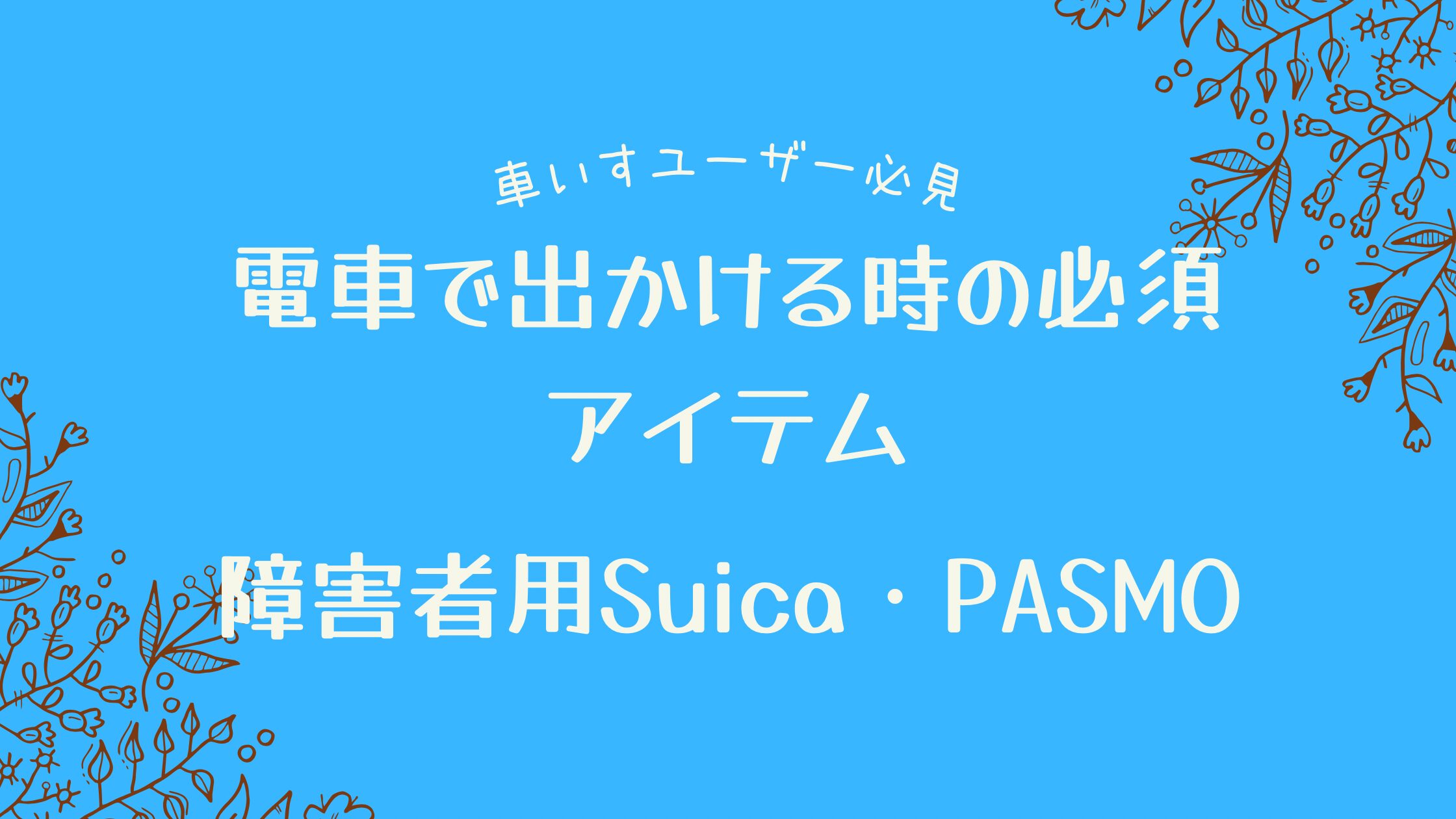
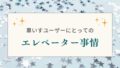
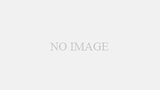
コメント